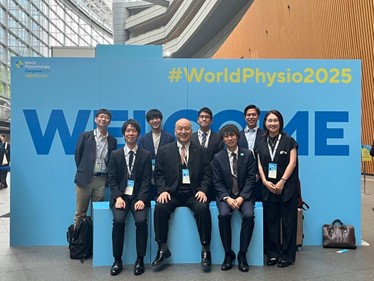2025年09月12日
【臨床身体機能学グループ研究紹介】World Physiotherapy Congress 2025での研究発表
2025年5月29日から31日にかけて、World Physiotherapy Congress 2025(世界理学療法会議2025)が東京国際フォーラムで開催されました。日本での開催は1999年の横浜大会以来、実に約四半世紀ぶりであり、今回が2回目となります。会議には127の国と地域から4,000人以上が集い、理学療法の最新動向を共有しました。なお、World Physiotherapyは1951年に設立された国際組織であり、世界的な理学療法士のネットワークを牽引しています。
今回の大会は、臨床知識や最新研究の発表を通じて国際的な交流を促進する場として位置づけられており、演題応募数は過去最多となる3,355件に達しました。これは2011年アムステルダム大会の記録(2,883件)を大きく上回り、世界101の国と地域から寄せられたもので、関心の高さを物語っています。
日本らしい演出も取り入れられていましたので少しご紹介しますと、開会式では、日本の伝統文化を取り入れたOrientarhythm(ダンスパフォーマンス)が披露されました。日本の武術にみられる「動」と「呼吸」のリズムや精神性を映像と融合させた演出は、多くの参加者に強い印象を与えました。また、会議の朝には日本伝統のラジオ体操が取り入れられ、世界各国からの参加者が一斉に体を動かしました。健康文化として根付く日本らしい習慣を国際的な舞台で共有する、貴重な機会となりました。さらに、プログラム内にはIdobata Sessions(「囲炉裏」を意味するインフォーマルな発表形式)が設けられ、話し手と参加者が自由に意見を交わす空間が提供されました。形式にとらわれない議論の場として大いに活用され、交流の輪が広がりました。

非常に盛会となった今回のWorld Physiotherapy Congress 2025で、本学からは臨床身体機能学グループの鈴木俊明 副学長、文野住文 准教授、東藤真理奈 講師、福本悠樹 講師、井尻朋人 客員准教授が発表し、また谷埜予士次 教授の指導のもと、準研究員の法所遼汰先生と河野達哉先生も研究成果の発表を行いました。以下に簡単に紹介いたします。
F-wave testing, an index of spinal cord anterior horn cell excitability, does not require supramaximal stimulation, submaximal stimulation is sufficient. (Toshiaki Suzuki, Marina Todo, Yuki Fukumoto, Makiko Tani, Naoki Kado, Fumiaki Okada, Masaaki Hanaoka)
脊髄前角細胞の興奮性の指標であるF波を検査するためには、α運動神経に強い電気刺激を与える必要があります。今回、通常より強度を低くしてもF波が記録できることを発見しました。
Combination of action observation and motor imagery, and motor imagery alone facilitates spinal motor neurons excitability than action observation alone. (Yoshibumi Bunno, Toshiaki Suzuki)
本研究により、運動観察のみよりも、運動観察しながら運動をイメージした方が脊髄運動神経の興奮性を高めやすいことが分かりました。また、運動イメージと運動観察の併用と運動イメージ単独ではその効果は同程度でした。運動イメージのみを行うか、もしくは観察を併用するかは、対象者に応じて考えていく必要があります。
Spinal motor nerve function necessary for the acquisition of hand motor skills. -Characteristics of motor units evaluated from F-wave waveforms- (Marina Todo, Yuki Fukumoto, Toshiaki Suzuki)
誘発筋電図の1つであるF波は、様々な運動単位の発火によって構成されるため多様な波形が記録されることが特徴です。しかし記録する筋に収縮を加えることで一定の波形の形に収束を認めることがあります。この特徴に対して独自の指標を用いて分析した結果を報告しました。
Age bias in changes in finger dexterity and spinal motor nerve function induced by motor imagery. (Yuki Fukumoto, Marina Todo, Hiroki Bizen, Daisuke Kimura, Toshiaki Suzuki)
運動イメージ効果が若年者と高齢者にどのように現れるかを検討しました。その結果、高齢者であっても若年者と同様に、運動イメージによる脊髄運動神経機能の変化と運動技能の向上が期待できることが明らかとなりました。
Relationship between scapular muscles activities balance and muscle strength in patients with shoulder disorders. (Tomohito Ijiri, Toshiaki Suzuki)
肩関節に疾患を持つ患者さんにおいて、腕を挙げる際の肩甲骨周囲筋活動について分析しました。筋力低下の大きな方ほど僧帽筋上部線維の筋活動が他に比べて大きくなる代償的な動きになることを報告しました。
Characteristics of lower extremity isometric strength and single-leg hops after 8 months in patients with anterior cruciate ligament reconstruction. (Ryota Hosho, Masayuki Yasuda, Yoshitsugu Tanino, Takeshi Sugimoto)
膝前十字靱帯(ACL)の再建術後8ヵ月経過した時点のスポーツ選手と健常な大学バスケットボール選手の下肢機能を比較しました。ACL再建術後では、理学療法の効果で股関節まわりの筋力は強くなっていましたが、膝関節の筋力と片脚幅跳びの結果は回復途中であることが分かりました。
Motion analysis of sidestep cutting in football simulating pressing situations: A focus on anterior cruciate ligament injury risk factors. (Tatsuya Kono, Yoshitsugu Tanino, Noriyuki Kida)
サッカーにおけるプレッシング場面で、膝前十字靭帯(ACL)損傷が多く発生している現状があります。今回、プレッシング場面でのサイドステップカッティング動作を再現し、三次元動作解析によってACL損傷リスクが増加する可能性をバイオメカニクス的に示しました。
今後も世界へ大きく発信していきたいと思っています。